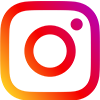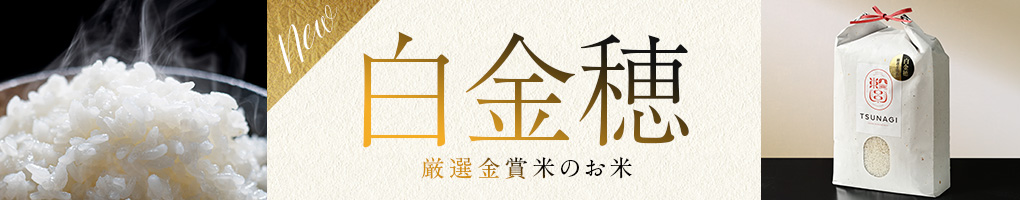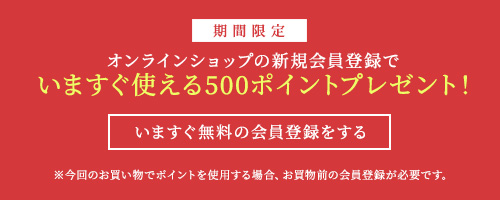はじめまして、あぐりきっずの太田です。
昨年は僕にとってあぐりきっずに入社してから、初めての米作りの年でした。社長の坂崎さんから自由に栽培を行っても良い、と僕と宮川さんにそれぞれ圃場をひとつ任され、そこでみどり豊の栽培に取り組む事となりました。
今まで家の手伝いや農業大学校で稲作に取り組んできましたが、栽培計画の立案から始めるのは初めてのことで、いざ始まってみると計画通りにならないことが多く、苦心の連続でした。ですが、初めから終わりまで自分でやってみて、そこで見つかる新しい発見や経験などが沢山あり、また改めて農業の楽しさを知ることが出来ました。
そんな去年の体験を米作りの時期を追って書いていこうと思います。
【2月】初めての栽培計画
僕の担当する田ではみのる産業さんのポット苗を使った成苗移植での栽培を行うことになりました。ポット苗は成苗の状態で田植えができるので田植え後の活着が2~3日で終わり、背丈があるために雑草対策の深水管理を行っても苗が沈むことなく行える。また、疎植栽培が出来るので1株に十分な日照とスペースが確保され、1株あたりの分げつ数が増加しやすい等と有機栽培に適しています。
丁度、僕も今回は
合鴨を使った有機無農薬栽培に取り組もうと考えていたので、この技術と組み合わせればより良いものになるのではないかと思い、成苗栽培基準で栽培計画を立てました。抽象的な内容は、全体的な施肥量を減らしその分を合鴨のフンでまかなおう、というものでした。また、肥料体系以外には鴨を飼育するスペースの設置や、害獣から防ぐための防獣ネットの設置なども計画していました。
【3月上旬】土を知って、土をいじる
3月に入り、まず初めに、圃場に籾殻薫炭を散布しました。燻炭を撒いたのは多孔性であり形状の残っている炭を土中に混ぜることで、通気を図るためでそれにより微生物の活発化、根の伸長を助ける効果、酸性土の中和を行う等様々な良い効果をもたらすと知ったからです。
今回使用した籾殻薫炭は、同じ市内にあるあいとうマーガレットステーションの横にある『菜の花エコプラザ』にて作られており、菜の花エコプラザでは燻炭作成時に排出される熱を利用し、館内に配置されたパイプを通して冬季には暖房として利用されています。一度エネルギーとして使用された籾を田圃に還元することは、無駄なエネルギーを余すことなく利用されすごくエコだなぁと思いました。
⇒次回、【3月下旬】ヘアリーベッチの効果に続く
こちらからあぐりきっずさんのお米をご購入できます⇒あぐりきっずさんのお米