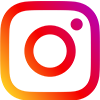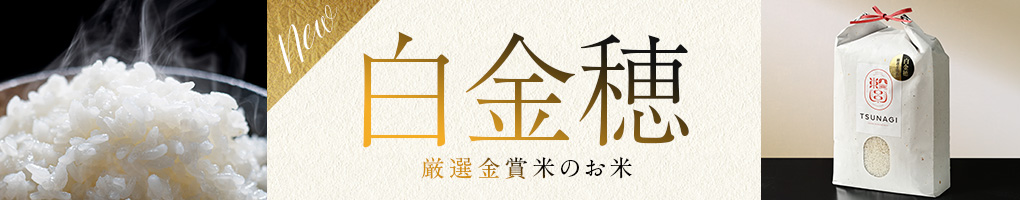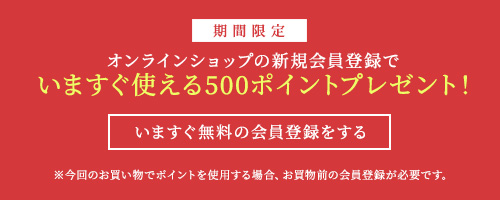「国産米と輸入米、結局どっちがいいの?」——スーパーで米を選ぶとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?
国産米は品質が高いと言われる一方、輸入米は価格の安さが魅力。しかし「輸入米の安全性は大丈夫?」「国産米と比べて味は?」といった不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、国産米と輸入米の違いを専門家の視点から解説し、味・安全性・コスパの観点で比較します。この記事を読めば、自分に合ったお米を選ぶヒントが見つかるはずです。

国産米と輸入米の基本的な違い
そもそも輸入米とは?
輸入米とは、海外で生産され、日本へ輸入されるコメのことです。主に業務用や加工用に使われることが多いですが、一部は家庭用としても流通しています。
国産米の定義と特徴
国産米とは、日本国内で生産・収穫された米のこと。品種改良や厳格な品質管理のもとで栽培されており、「コシヒカリ」「あきたこまち」などのブランド米が有名です。国産米は、日本の米作りに特化した技術と厳格な基準があるため、安定した品質が保たれています。また、国産米は消費者からの信頼感も強く、日本国内での人気は非常に高いです。
輸入米の主な産地と種類
輸入米は主に以下の国々から輸入されます。これらは日本の食文化に馴染みやすいですが、風味や食感は国産米と異なるため、好みによって選ぶことが重要です。
•アメリカ(カリフォルニア州):カルローズ米が有名。やや粘りが少なく、パラパラとした食感で、比較的安価で流通している。
•タイ:インディカ種(タイ米)が主流で、パラパラとした食感が特徴。カレーや炒飯に向いている。
•中国:日本と同じジャポニカ種だが、品種や栽培環境の違いなどから、やや甘みや粘りが少なく感じられることがある。
•オーストラリア:高温・乾燥した気候で育てられた品種が多い。長粒種や中粒種が栽培され、主に加工用として利用される。
国産米と輸入米の味や品質の違いを比較

食味・食感・香りの違い
•国産米:ふっくらとした粘りと甘みが特徴。香りも豊かで、日本人の食味や和食に合っている。冷めても美味しい品種も多い。
•輸入米:産地によって異なるが、カリフォルニア米(カルローズ米)は軽い食感で、炒飯やサラダ向き。タイ米(インディカ種)はパラパラした食感で、カレーやエスニック料理に適しています。
•香りの違い:国産米は穏やかな甘い香り、ジャスミンライス(タイ米)などは独特の芳香がある。
品種や栽培方法の違いによる影響
国産米は、温暖湿潤な気候を生かした水田栽培が主流です。一方、アメリカやオーストラリアでは人工的に水を供給して作物を栽培する大規模な灌漑農業(かんがいのうぎょう)が行われており、品種だけでなく生育環境も異なるため、食感や味わいにも違いが出ます。
炊き方のポイントとおいしく食べるコツ
•国産米:水加減を適切に調整し、炊飯時に10~15分蒸らすと美味しく仕上がる。
•カルローズ米(アメリカ産):少なめの水で炊くか、ピラフ・リゾット向きに調理すると美味しい。
•タイ米(インディカ種):多めの水で炊き、ざるで水を切るとパラパラ食感が際立つ。粘りがなく、カレーやエスニック料理に向く。
安全性・残留農薬・放射能などの比較

国産米の安全基準と検査体制
国産米は、農薬や放射能に関する厳しい基準が設けられています。農産物には「農薬残留基準」が定められ、出荷前に厳格な検査が行われます。米作りに使用される農薬は、適切な使用量が定められており、農薬の種類や使用回数にも制限があります。これらの基準を超えて農薬が使用されることはなく、米が出荷される前に農薬の残留量を検査し、基準値を超えるものは市場に流通しない仕組みです。
また、日本では農産物に対して非常に高いレベルのトレーサビリティ(追跡可能性)を確保しています。コメの場合、生産地や生産者情報がラベルに記載されており、購入した米の産地や検査結果を確認することができます。これにより、消費者は自分が購入する米がどの地域でどのように栽培されたのかを知ることができ、安全性に関する信頼感を持つことができます。
このような基準や検査体制から、国産米の安全性は非常に高いと言えます。
輸入米の安全基準とチェックポイント
輸入米も、各国の安全基準に基づき輸入されますが、日本国内の基準とは異なることがあります。また、ポストハーベスト(収穫後の農薬使用)が問題視されることもあります。
そのため、輸入米を選ぶ際は、必ず信頼できるブランドや、認証機関のチェックを受けたものを選ぶことが重要です。また、輸入米は長期間の輸送を経るため、品質にばらつきが生じることもあります。
輸入米は本当に安全?よくある誤解を解説
「輸入米は危険だ」という誤解を持つ人もいますが、実際には、多くの輸入米は日本の基準をクリアしており、安全性の問題は少ないです。ただし、産地や生産者によって品質や管理体制に差があるため、選ぶ際には注意が必要です。「輸入米=危険」というわけではありませんが、購入の際には信頼できる産地や流通経路を確認することが重要です。
価格・コストパフォーマンスの違い
国産米の価格相場と価格帯ごとの特徴
国産米は、品種や生産地によって価格が異なります。特に人気のある「コシヒカリ」などは高めの価格帯に位置していますが、他の品種や業務用のコメは比較的安価で購入できます。2024年8月の令和の米騒動以降、相場が上がっていますが、価格の安定を目指して2025年は備蓄米の放出が進められています。今後の相場動向については不透明ですが、一般的に国産米は輸入米よりも高価格です。
輸入米の価格メリットとデメリット
輸入米は比較的安価で、業務用として使われることが多いですが、炊き方や用途を選ぶ必要があります。つまり、輸入米の最大のメリットは、価格の安さです。カルローズ米などは、コストパフォーマンスに優れており、大量に消費する飲食店や家庭にとっては、経済的な選択肢となります。ただし、品質にばらつきがあることを考慮しなければならない点がデメリットと言えるでしょう。
結局どちらがコスパが良い?
飲食店では、コストパフォーマンスを重視して輸入米が選ばれることもありますが、家庭用では品質や味を重視し国産米を選ぶのが一般的です。用途や目的に応じた使い分けが重要です。
国産米と輸入米は結局どちらが良い?

目的やニーズに応じた選び方をご提案
結局のところ、国産米と輸入米、どちらが良いのでしょうか?その答えは、目的やニーズに応じて選ぶのがベストと言えるでしょう。品質を重視したいなら、国産米をおすすめします。家庭でのお米は、味や食感を重視するならば国産米を選ぶと間違いないでしょう。一方、コストを抑えたい場合は、輸入米も十分に選択肢に入ります。サラダ、ピラフなどに使う場合には、カルローズ米(カリフォルニア米)が適しています。どちらを選ぶにしても、信頼できる生産者やブランドを選ぶことが大切です。
専門家(米・食味鑑定士)としての見解・おすすめシーン
日常的に食べるならやはり国産米をおすすめします。米専門店としての見解ですが、2025年以降は、地域性や栽培方法にこだわりを持った国産米の需要が増えていくと予想しています。特に、減農薬や有機栽培のお米を選ぶことで、より安全で美味しいお米を選ぶことができます。輸入米は、食事のバリエーションを増やす目的で使うことで、お米選びの選択肢を広げ、新たなお米の楽しみ方が見つかるかもしれません。
参考:米をめぐる状況について(令和6年8月)|農林水産省https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/240827/attach/pdf/240827-4.pdf
参考:米に関するマンスリーレポート(令和7年2月)|農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-917.pdf
関連コラムはこちら→2025年お米価格高騰!ついに備蓄米放出!?
新規生産者のお米

会津猪苗代カンダファーム(神田忍)さんの
福島県猪苗代町産ゆうだい21(2kg)
2024年 第26回 米・食味分析鑑定コンクール国際大会 国際総合部門 金賞粒の大きさと美しさ、粘りと弾力、そして噛むほどに広がる深い甘みを感じられます。お米本来のおいしさを引き出す栽培方法で育てました。

横山農産サービス(横山忠弘)さんの
岡山県美作市産コシヒカリ(特別栽培米)
山々に囲まれた自然豊か地域で、日名倉山から冷たくミネラル豊富な水が流れ込みます。粒がしっかりと大きく、艶やかな外見が特徴です。炊き上がりの食感もふっくらとしており、粘りと甘みが感じられます。

冨田和孝さんの
熊本県菊池市産天然菌味噌(黒大豆)
冨田和孝さんのオリジナル「天然菌味噌(黒大豆)」は、20年以上も農薬や化学肥料を一切使用せず自然栽培された黒大豆と米を原料とし、自然の力で発酵させた贅沢な味噌です。約100年間蔵に定着した4種類の麹菌による豊かな風味を楽しめます。